三種【法規】の試験では、電気事業法以外に出題される法規問題があります。それは、
- 電気用品安全法
- 電気工事士法
- 電気工事業法
です。
出題されるのは1問程度ですが、覚える範囲はそこまで多くありません。この記事では、電気工事業法の重要な点をまとめましたので、出たら得点できるようにポイントを押さえましょう!
電気工事業法
目的
(目的)
第一条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
電気工事業法の目的について、条文の穴埋めが良く出題されます。赤字箇所が良く穴埋めにされます。
電気工事業者の分類
電気工事業者は、
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
に分類されます。
登録電気工事業者
- 登録電気工事業者は、一般用電気工作物を含む電気工事業(一般用電気工作物のみ、または一般用電気工作物と自家用電気工作物の工事)を営む電気工事業者
- 事業を営むためには都道府県知事(一つの都道府県のみの営業の場合)または経済産業大臣(二つ以上の都道府県で営業の場合)の登録を受けなければならない
- 登録の有効期間は5年
通知電気工事業者
- 通知電気工事業者は、自家用電気工作物のみの電気工事業を営む電気工事業者
- 事業を営むためには都道府県知事(一つの都道府県のみの営業の場合)または経済産業大臣(二つ以上の都道府県で営業の場合)に、事業を開始する日の10日前までに通知しなければならない
電気工事業者の業務
- 登録電気工事業者は、営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後三年以上の実務経験を有するものを、主任電気工事士として置かなければならない
- 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
- 一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
- 電気工事業者は電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させてはならない
- 電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない
- 電気工事業者は、電気用品安全法に適合している電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない
- 電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の器具を備えなければならない
- 電気工事業者は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名又は名称、登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
- 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載し、5年間保存しなければならない
まとめ
- 電気工事業法の目的は、業務の適正な実施と電気工作物の保安の確保
- 電気工事業者には、「登録電気工事業者(一般用電気工作物を含む電気工作物の工事業者)」と「通知電気工事業者(自家用電気工作物のみの工事業者)」がある
- 登録は5年間有効
- 帳簿の保存期間は5年
- 登録電気工事業者は営業所ごとに主任電気工事士を置かなければならない
- 主任電気工事士は、第一種又は第二種電気工事士資格取得後、実務経験3年以上を有していなければならない
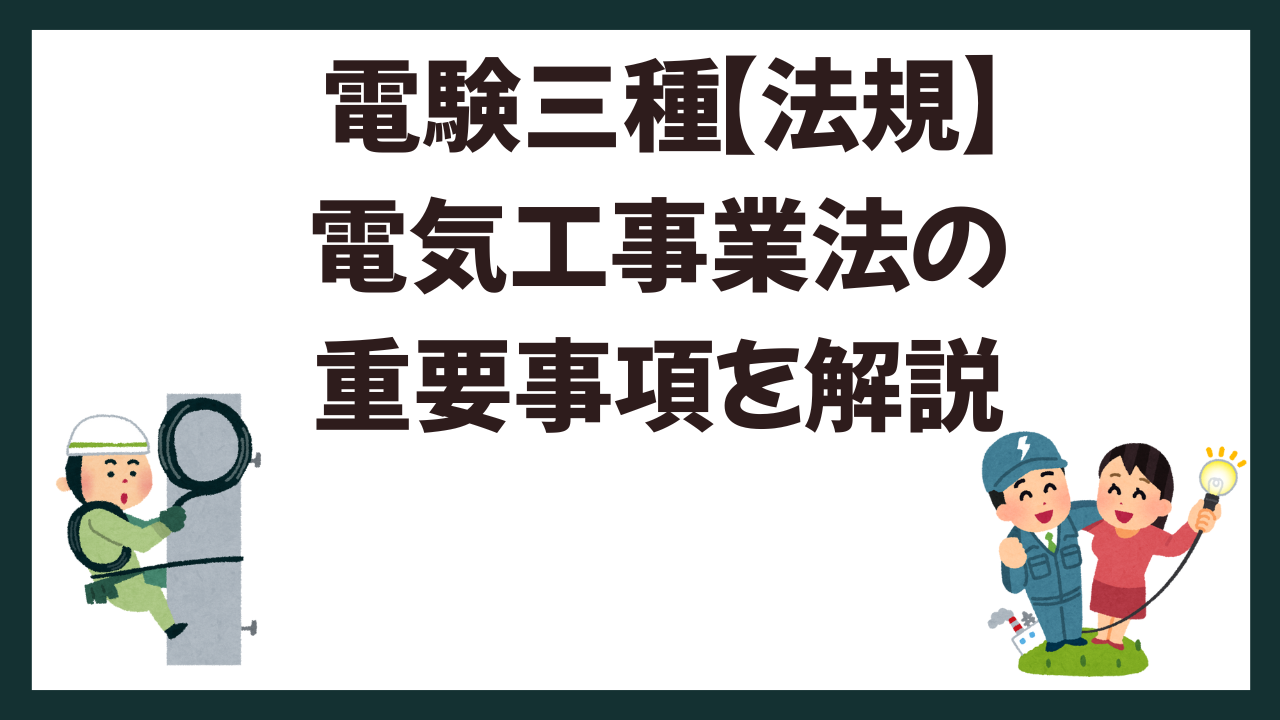

コメント